 |
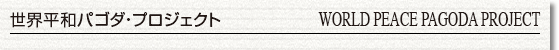 |
 |
北九州市門司区の和布刈公園に建つ「世界平和パゴダ」は、日本で唯一のビルマ式寺院です。第二次世界大戦後、ビルマ政府仏教会と日本の有志によって昭和32年(1957年)に建立されました。「世界平和の祈念」と「戦没者の慰霊」が目的でした。
戦時中は門司港から数多い兵士が出兵しました。映画化もされた竹山道雄の名作『ビルマの竪琴』に登場する兵士たちです。残念なことに彼らの一部しか、再び祖国の地を踏むことができませんでした。そこでビルマ式寺院である「世界平和パゴダ」を建立して、その霊を慰めようとしたわけです。しかしウ・ケミンダ大僧正の死後、パゴダは資金難のため、休館されていました。
2012年3月3日、ウ・ケミンダ大僧正の「お別れ会」が門司倶楽部で開かれました。パゴダ建立の最大の立役者である旧門司市の故・柳田桃太郎市長のご令嬢である八坂和子さんのお骨折りで実現した会でした。そのお世話をさせていただいたご縁で、わが社がパゴダと関わりを持つことになりました。
同年8月25日にミャンマー大使館を訪れた佐久間進サンレーグループ会長とわたしは、キン・マゥン・ティン大使とミャンマー仏教界の最高位にあるエンダパラ大長老にお会いしました。そして、お二人から佐久間会長が重大なミッションを授かりました。そのミッションとは、閉鎖されている世界平和パゴダの再開に向けて、ミャンマーと日本の仏教交流組織を正式に発足させ、父が代表に就任するというものでした。
その組織は「日緬仏教文化交流協会」と名づけられ、以下のメンバーが選出されました。
会長:佐久間進(サンレーグループ会長)
理事:鎌田東二(京都大学こころの未来研究センター教授)
理事:井上ウィマラ(高野山大学准教授)
理事:井上幸一(農業資源開発コンサルタント)
理事:八坂和子(宗教法人世界平和パゴダ理事)
委員:佐久間庸和(株式会社サンレー社長)
同月28日、北九州に三人のミャンマー僧が来られました。エンダパラ大長老を筆頭に、新たにミャンマーから世界平和パゴダに派遣されたウ・ウィマラ長老とウ・ケンミェイタラ僧です。新しく赴任されたお二人は翌29日の夜から世界平和パゴダで生活を始めました。つまり、8月29日をもって「世界平和パゴダ」が再開されたことになったのです。
世界平和パゴダ再開にあたっての記者会見の席上で、佐久間会長は「世界平和パゴダはビルマ戦線での戦没者の慰霊塔のようなイメージが強いですが、もともとパゴダとは聖なる寺院です。この聖地を一日も早く復活すべく微力ながらお手伝いさせていただくことになりました。わたし個人としては、日本が無縁社会を乗り越えるための拠点にもしたいと考えています」と述べました。
また、わたしは「『無縁社会』とか『孤族の国』といった言葉があります。日本人のこころの未来は明るいとは言えません。このような状況を乗り越えるシンボルに世界平和パゴダはなり得ると思います。日本で唯一の上座部仏教の聖地であり、ブッダの骨を収める仏舎利も有していることから観光的資源としても大きな可能性を持っています。さらには、建築デザインも素晴らしく、平和のモニュメントとしての意味も限りなく大きいと言えます。わたしは、将来的に広島の原爆ドームと同じく『世界文化遺産』にすることも夢ではないと考えており、ぜひ、ユネスコに申請したいと思っています。諸々のことを含めて、世界平和パゴダの意義と重要性を広く発信していきたいです」と申し上げました。ユネスコ・世界文化遺産申請のアイデアは大使から大変喜ばれ、会見終了後には「全面的に協力させていただく」とのお言葉を頂戴しました。
ミャンマーは上座部仏教の国です。上座部仏教は、かつて「小乗仏教」などとも呼ばれた時期もありましたが、ブッダの本心に近い教えを守り、僧侶たちは厳しい修行に明け暮れています。
現在の日本は韓国・中国・ロシアなどと微妙な関係にある国際的に複雑な立場に立たされています。わたしは、ミャンマーこそは世界平和の鍵を握る国であると心から思っています。「寛容の徳」や「慈悲の徳」を説く仏教の思想、つまりブッダの考え方が世界を救うと信じているのです。平和の風は、門司から世界に向かって吹くことでしょう。
|
 |
|
 |
|
 |
 |
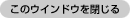 |
 |
|
 |
|