 |
 |
 |
私はマザー・テレサを心の底から尊敬しています。
「私があなた方を愛したように、あなた方も、相愛しなさい」というイエスの言葉にマザーの一生は要約されていると言っていいでしょう。イエスが行なった無償の愛を20世紀後半に実行した人であり、宗教、民族、年齢、性別、社会的地位などに一切関わりなく、必要とする人々に愛の手を差し伸べた人でした。
ある日のこと、マザーは、歩道で死にかけている女性を見つけました。彼女の苦しみを和らげ、ベッドで心静かに人間らしく死なせてやりたいと思って、女性を連れて帰りました。この愛の行為をきっかけとして、マザーは、1952年8月に「清い心の家」にルマン・ヒリダイとも呼ばれる「死を待つ人の家」を開設することになりました。
「死を待つ人の家」では、数え切れないほど多くの死にゆく人々を看取りました。マザーは、ヒンドゥー教やイスラム教の人が亡くなるときは、その宗教のお経を唱えて送ってあげました。マザーの活動の源泉はカトリックの神への信仰でしたが、その根源にあるものは、人間の生命は限りなく尊いというイエスの教えであり、それこそ、一神教や多神教といった枠組みを超えて今後のすべての宗教のあるべき姿を示したのでした。それを失うと、宗教とは心の狭い原理主義に陥り、最後は戦争にまでつながります。
マザー亡き後も、インドのカルカッタでは彼女の後継者たちが「死を待つ人の家」を守っています。死にゆく人々は栄養失調から来る衰弱死のため、たいていは苦悶の表情を浮かべて死んでいきますが、いまわのきわに口に氷砂糖やチョコレートなどを含ませると、ニッコリと笑って旅立ってゆくそうです。また、亡くなった人は当然ながら貧しく葬儀をあげることはできませんが、せめてもの人間の尊厳として白い布が遺体にかけられます。
その最期に口に含む氷砂糖やチョコレートはもちろん、死者の体を包む白布までもが不足しているというのです。サンレーは「人間尊重」をミッションとする企業であり、常々、「死は最大の平等である」とのテーゼを掲げ、その実現をめざしています。ぜひ、創業40周年を迎える2006年より、白布の大量寄贈をはじめとしたさまざまなサポートを「死を待つ人の家」に対して行なっていきたいと考えています。
天においては「月面聖塔」が、地においては「死を待つ人の家」が私たちを待っています。ムーン・ハートピア・プロジェクトも、マザー・テレサ・プロジェクトも、ともに「死は最大の平等である」の思想を実現する試みなのです。マザーが歩んだ道と、私たちがめざす道とは、同じ目的地へと続いていると確信しています。 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
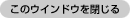 |
 |
|
 |
|